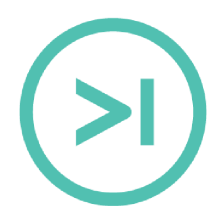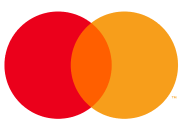此功能 由google翻譯提供參考,樂淘不保證翻譯內容之正確性,詳細問題說明請使用商品問與答
--- ### 悠久の時を超え、輝きを纏う:ヒュプノスの織物 #### 序章:眠れぬ夜のセレナーデ 東京の夜は、決して眠らない。煌々と輝く摩天楼の灯り、絶え間なく流れる車のヘッドライト、そしてどこからか聞こえてくるサイレンの微かな残響。それらは、私、水瀬天音(みなせ あまね)にとって、巨大な不協和音となって鼓膜を揺さぶり続けていた。 国立精神・神経医療研究センターの睡眠科学研究部に所属する助教として、私は「眠り」を科学のメスで切り刻むことを生業としている。レム睡眠とノンレム睡眠のサイクルが記憶定着に与える影響、概日リズムを司る視交叉上核のメカニズム、オレキシン神経系の覚醒維持機能――私の頭の中は、眠りに関する無数の専門用語とデータで埋め尽くされている。皮肉なことに、誰よりも眠りの重要性を理解しているはずの私自身が、もう半年以上も深刻な入眠障害と中途覚醒に苦しんでいた。 原因は複合的だ。行き詰まった研究、厳格な物理学者の父との長年の確執、そして一年前に終わりを告げた恋。聡(さとる)さん、あなたは今、どこでどんな研究をしているのだろう。私たちの別れは、まるで不完全な実験のように、結論の出ない問いだけを私の心に残していった。 処方された睡眠導入剤は、意識を無理やり刈り取るだけで、深い安らぎをもたらしてはくれない。浅い眠りの海を漂い、悪夢という名の海藻に絡めとられ、疲労だけを蓄積させて目覚める朝。モニターに映し出される自身の睡眠脳波データは、教科書に載せたいほどの見事な「質の悪い睡眠」を示していた。それは、研究者としての私に対する、身体からの痛烈な皮肉だった。 ある雨の土曜日、私は無意識に足を動かし、神保町の古書店街を彷徨っていた。目的もなく歩くうちに、裏路地にひっそりと佇むアンティークジュエリーの店が目に留まった。『時紡ぎの匣(ときつむぎのはこ)』と古風な書体で記された看板。吸い寄せられるように、錆びた真鍮のドアノブに手をかけた。 店内に満ちていたのは、古い木の匂いと、微かな白檀の香り。ガラス易碎品限空運,非易碎品可使用海運。 ケースの中には、アール・デコ様式のブローチや、ヴィクトリア朝の繊細な細工が施されたロケットペンダントが、過ぎ去った時間の中から静かに光を放っていた。 その中で、ひときわ強く私の視線を捉えたものがあった。 ベルベットのトレイの上に、まるで溶けた銀河が凝固したかのように横たわる、一本のネックレス。 「K18ホワイトゴールドの、トリプル6面カット喜平ネックレスでございます」 老店主が、私の視線に気づいて穏やかに言った。 それは、一般的に男性的なイメージの強い喜平ネックレスでありながら、驚くほど繊細で、優雅な気品を漂わせていた。幾重にも編み込まれたプラチナに近い白い輝きは、冷たい光沢の中に、どこか生命の温かみを宿しているように見える。一つ一つの面が複雑に光を反射し、見る角度によって無限の表情を作り出す。まるで、幾千もの夢の欠片を繋ぎ合わせたかのようだ。 「……美しい」 思わず、声が漏れた。 そのネックレスは、ただの装飾品ではなかった。それは、悠久の時を旅してきた物語そのもののように感じられた。私は値札も見ずに、震える声で言った。 「これを、ください」 それが、私の人生を根底から揺るがす、奇跡と再生の物語の始まりだった。 その夜、私はシャワーを浴びた後、祈るような気持ちでネックレスを首にかけた。20.49gという確かな重みが、鎖骨のくぼみに心地よく収まる。ひんやりとした金属の感触が、火照った肌を優しく鎮めてくれるようだった。鏡に映る自分の姿は、見慣れないほど落ち着いて見えた。ネックレスの白い輝きが、疲れた顔に不思議な光彩を与えている。 ベッドに入り、いつものように天井の染みを数え始める。しかし、その夜は違った。ネックレスが触れる首筋から、穏やかな波が全身に広がっていくような、不思議な感覚。意識が遠のいていく。それは、薬によって強制的に断ち切られる感覚とは全く違う、自らを優しく手放していくような、自然で心地よい眠りへの移行だった。 私は、深い、深い眠りの谷底へと落ちていった。 #### 第一章:過去への誘い - 母の微笑み 目を開けると、そこは見慣れた自室の天井ではなかった。高い天井から吊るされた、レトロなミルクガラス易碎品限空運,非易碎品可使用海運。 のランプシェード。壁にはセピア色の映画ポスター。そして、窓の外からは、けたたましいクラクションの代わりに、都電のチンチンという懐かしい走行音が聞こえてくる。空気に混じる、サイフォンで淹れたコーヒーの豊かな香り。 私は、クラシックな喫茶店の、深紅のベルベットが張られた椅子に座っていた。状況が全く理解できない。夢だ。あまりにも鮮明で、五感のすべてがリアルに反応している夢。 「天音、ぼーっとしてどうしたの?ほら、クリームソーダ、溶けちゃうよ」 目の前から、快活な声がした。顔を上げると、そこにいたのは、20代前半の頃の母だった。私が物心ついた頃にはすでに病気がちで、いつも儚げに微笑んでいた母とは違う。肩まで伸びた黒髪をポニーテールにし、大きな瞳を好奇心で輝かせている、生命力に満ちた女性。母が若き日に語ってくれた、思い出の喫茶店『ミモザ』。そのものだった。 「お母さん……?」 「もう、変な天音。さっきから心ここにあらずって感じよ。卒論、そんなに大変?」 母――美咲は、悪戯っぽく笑いながら、目の前のクリームソーダをストローでかき混ぜた。グラスの中で、鮮やかな緑と純白のアイスクリームが混ざり合い、しゅわしゅわと音を立てて泡が弾ける。 私は混乱しながらも、この非現実的な状況を受け入れ始めていた。これは、私の記憶ではない。母の記憶、あるいは母が生きていた時間そのものに、私が迷い込んだのだ。首元に触れると、ひんやりとしたネックレスの感触があった。この輝きが、私をここに連れてきたのだろうか。 「ねえ、天音。私、決めたんだ。やっぱり、絵本作家になりたい。浩一さんは、不安定な道だって心配してくれるけど、私は描きたい物語があるの」 浩一さん、それは父の名前だ。若き日の母は、父との未来を夢見ながら、自身の夢を熱っぽく語っていた。私が知っている、諦めと悲しみを滲ませた母の姿はどこにもない。 「子供たちの心に、小さな灯りをともせるような、そんなお話を描きたいの。たとえ世界がどんなに複雑で、辛いことがあっても、物語の中にはいつでも希望があるって、伝えたいから」 美咲の言葉は、私の心の奥底に眠っていた何かを優しく揺り動かした。私は、いつから希望という言葉を口にしなくなっただろう。データと論文に追われ、他者との比較に疲れ果て、自分自身の心を置き去りにしてきた。 「……きっと、なれるよ。お母さんなら」 思わず口から出た言葉に、美咲はきょとんとした顔をし、それから花が咲くように笑った。 「ありがとう、天音。あなたがそう言ってくれると、すごく勇気が出る」 その笑顔は、陽だまりのように温かかった。私は、この笑顔を守りたいと、心の底から思った。たとえこれが、一瞬の夢だとしても。 やがて、喫茶店の風景がゆっくりと白く霞んでいく。意識が浮上していく感覚。名残惜しさを感じながら、私は美咲の笑顔を目に焼き付けた。 はっと目覚めると、朝日がカーテンの隙間から差し込んでいた。午前7時。信じられないことに、一度も目を覚ますことなく、8時間も眠り続けていたのだ。身体の芯に残っていた鉛のような疲労が、嘘のように消え去っている。爽快感と、満たされた感覚。こんな目覚めは、何年ぶりだろう。 急いでスマートウォッチを確認する。睡眠アプリが記録したデータは、私の驚きを裏付けていた。深いノンレム睡眠(徐波睡眠)の割合が通常時の3倍近くに達し、レム睡眠とのサイクルも理想的な曲線を描いている。心拍数も安定し、ストレスレベルは測定開始以来の最低値を記録していた。 科学者としての私が、この異常なデータを前に警鐘を鳴らす。「プラセボ効果の範疇を超えている。何らかの生理的変化が起きていることは間違いない」。しかし、一人の人間としての私は、ただただこの安らかな眠りの余韻に浸っていた。 私は研究室のデスクで、昨夜の体験について考察を始めていた。自分の論文執筆の手を止め、真っ白なノートに書き出す。 『仮説1:ネックレスは、特定の周波数を持つ微弱な電磁波、あるいは超音波を発生させ、脳の松果体におけるメラトニン分泌を促進している?いや、それだけではあの鮮明な夢、過去への介入とも思える体験は説明できない』 『仮説2:これは、ユング心理学における「集合的無意識」へのアクセスか?ネックレスが触媒となり、個人的な無意識の層を突き抜け、人類共通の元型的な記憶領域に接続した?母の記憶にアクセスできたのは、血縁という繋がりがアンカーとなったからか?』 そこで、ふと数年前に読んだ論文を思い出した。オックスフォード大学のロジャー・ペンローズとアリゾナ大学のスチュート・ハメロフが提唱した「Orch-OR理論(Orchestrated Objective Reduction theory)」だ。この理論は、意識がニューロンの発火という古典的な計算プロセスから生じるのではなく、脳細胞内の微小管(マイクロチューブル)で生じる量子効果、すなわち「客観的収縮」によって生まれると主張する、極めて野心的な仮説である。 『もし、意識が量子現象であるならば、時間や空間の制約を受けない「量子もつれ(エンタングルメント)」のような非局所的な繋がりを持つ可能性も否定できない。睡眠中、特に脳がシータ波優位となるレム睡眠期において、脳内の量子状態は外部からの影響を受けやすくなる。K18ホワイトゴールドという特定の貴金属の格子構造、そしてトリプル6面カットという複雑な幾何学的形状が、何らかの量子共振器(Quantum Resonator)として機能し、私の意識の量子状態を、過去の特定の時空座標に存在する情報場とエンタングルさせた……?』 馬鹿げている。そう頭では思いながらも、私の指は興奮に打ち震えながらノートの上を滑っていた。これは、私の専門分野である睡眠科学と、父の専門である理論物理学が、思いがけない形で交差する領域だった。もしこの仮説が少しでも真実なら、私はとんでもない扉を開けてしまったことになる。 その夜も、私はネックレスを身につけて眠りについた。次は何を見るのだろう。期待と、少しの恐怖を胸に抱きながら。 #### 第二章:確執の根源 - 父の涙 次に私が見た光景は、大学の研究室だった。古い計算機が並び、黒板には数式がびっしりと書き殴られている。そして、そこにいたのは、若き日の父、水瀬浩一だった。白衣を着て、無精髭を生やし、分厚い眼鏡の奥の瞳をギラギラと輝かせている。私が知る、感情を表に出さず、常に厳格で、私の研究を「お遊びだ」と一蹴する父とはまるで別人だった。 彼は、数人の大学院生仲間と、熱っぽく議論を交わしていた。 「時空の構造は、我々が観測する4次元に留まらないはずだ。超ひも理論が予測するように、高次元空間がコンパクト化されているとすれば、その余剰次元を通じて、異なる時空との情報のやり取りが可能になるかもしれない!」 その情熱、その探究心。それは、かつて私が科学の道を志した時に抱いていたものと、全く同じ種類のものだった。私は、父のこんな姿を一度も見たことがなかった。 場面が変わり、父は一人、大学の屋上で煙草をふかしていた。そこに、一人の女性が駆け寄ってくる。若き日の母、美咲だ。 「浩一さん!またこんなところにいた。身体に悪いわよ」 「……美咲か。すまない、少し考え事をしていた」 父は、母の前では少しだけ表情を和らげる。 「論文、上手くいかないの?」 「ああ。僕の仮説は、あまりに突飛すぎて、誰も本気で取り合ってくれない。だが、僕は間違っているとは思えないんだ。この宇宙には、我々がまだ知らない、とてつもない秘密が隠されているはずなんだ」 その時、私は父が私に言い放った言葉を思い出していた。「天音、科学というのは、証明可能な事実を積み重ねていく地道な作業だ。お前がやっている睡眠と意識などという曖昧なテーマは、科学ではなく哲学か文学の領域だ」。 あの言葉は、一体何だったのだろう。目の前にいる、誰よりもロマンチストで、未知なるものに情熱を燃やすこの青年が、なぜあんなにも冷たく、現実的な人間になってしまったのか。 夢の中の時間は、残酷に、そして慈悲深く進んでいく。 父と母は結婚し、私が生まれた。小さなアパートでの、貧しいけれど幸せな日々。しかし、その幸せに影が差し始める。母の身体を、病魔が蝕み始めたのだ。日に日に弱っていく妻を前に、父の表情から輝きが消えていく。 ある夜の光景が、私の胸に突き刺さった。 病院の待合室の長椅子で、父は一人、肩を震わせていた。手には、母の病状が記された診断書が握りしめられている。彼は、声を殺して泣いていた。理論物理学で宇宙の謎を解き明かそうとしていた男が、愛する妻一人の身体を蝕む病という、あまりにも現実的な脅威の前で、なすすべもなく打ちひしがれている。 「なぜだ……」父の嗚咽が聞こえる。「どんな難解な数式よりも、なぜ君を救う方法の一つも見つけられないんだ……。僕の科学は、無力だ。あまりにも、無力だ……!」 その時、私はすべてを理解した。 父が科学に対して厳格になったのは、情熱を失ったからではなかった。むしろ逆だ。彼は、科学を愛し、その可能性を信じすぎていたのだ。そして、その科学が、最も愛する人を救えなかったという絶望的な無力感が、彼の心を硬く、冷たい鎧で覆ってしまったのだ。彼が私の研究を否定したのは、私を憎んでいたからではない。彼がかつて夢見て、そして打ち砕かれた「証明できない領域」に、愛する娘が足を踏み入れることを、恐れていたのだ。私に、自分と同じ絶望を味わわせたくなかったのだ。 私は、若き日の父の背中に向かって、何度も何度も叫んだ。 「お父さん、ごめんなさい。私、何も知らなかった……!」 もちろん、声は届かない。しかし、私の涙は、時空を超えて、彼の孤独な魂に寄り添っているような気がした。 目覚めた時、私の枕はぐっしょりと濡れていた。しかし、心は不思議なほど穏やかだった。長年、私と父の間を隔てていた分厚い氷の壁が、音を立てて溶け始めたのを感じた。 私は、受話器を取った。震える指で、実家の電話番号をダイヤルする。何年も、事務的な連絡以外で電話などしたことがなかった。 「……もしもし」 電話の向こうから、聞き慣れた父の低い声がした。 「お父さん、私、天音。……あのね、今度の日曜日、帰ってもいいかな」 一瞬の沈黙。そして、電話の向こうで、父が小さく息を呑む音がした。 「……ああ。待っている」 それは、たったそれだけの会話だった。しかし、私と父にとっては、何万もの言葉よりも重い意味を持つ、和解への第一歩だった。 デスクに戻り、再びノートを開く。今度は、心理学的な考察を書き加えた。 『エピジェネティクス(Epigenetics)の分野では、親が経験した強いストレスやトラウマが、DNAのメチル化などの化学修飾を通じて、子の世代の遺伝子発現に影響を及ぼす可能性が示唆されている。父が抱えた絶望と無力感。母を失った喪失感。それらは、目に見えない形で私に受け継がれ、私の神経系、特にストレス応答や情動を司る扁桃体や海馬の機能に影響を与え、不眠の一因となっていたのではないか』 『ネックレスを介した過去への旅は、単なるタイムスリップではない。それは、私自身のルーツを辿り、家族の物語を追体験することで、世代間で受け継がれたトラウマを認知的に再評価し、その呪縛から自らを解放する、一種の心理療法(Psychotherapy)的なプロセスなのかもしれない』 私の研究は、新しい局面を迎えようとしていた。それはもはや、単なる睡眠科学ではなかった。物理学、心理学、そして歴史学さえも内包する、壮大な「意識の考古学」だった。 #### 第三章:別離の真実 - 聡の後悔 次なる眠りが私を運んだのは、それほど遠くない過去だった。一年前の、雨が降りしきる夜。場所は、私と聡さんがよく待ち合わせをした、大学近くの公園の東屋だ。 「別れよう、天音」 聡さんの声が、冷たい雨音に混じって響く。傘を持つ彼の指が、白くなるほど強く握りしめられているのを、私は見ている。当時の私には、その言葉の冷たさしか聞こえていなかった。なぜ?どうして?私の何がいけなかったの?と、混乱と悲しみで頭がいっぱいだった。 しかし、時空を超えた観察者として、今の私には見えるものがあった。彼の横顔に浮かぶ、深い苦悩。唇を噛みしめる微かな震え。そして、私を見つめる瞳の奥に揺らめく、痛々しいほどの優しさと、後悔の色。 「君の研究は、素晴らしい。その独創性、着眼点、そして何より情熱……君は、僕なんかとは違う。きっと、世界的な研究者になる」 「何よ、それ……」 「僕は、もう限界なんだ。自分の才能の無さに、とっくに気づいてる。このまま君の隣にいたら、君の輝きに嫉妬して、君の足を引っ張るだけだ。僕は、そんな惨めな男にはなりたくない」 当時の私は、それを言い訳だと思った。私から離れるための、卑怯な口実だと。しかし、今の私には、彼の言葉が、血を吐くような本心からの叫びであることが痛いほどわかった。 聡さんは、誰よりもプライドが高く、そして誰よりも繊細な人だった。彼は、私の才能を心から信じ、愛してくれていた。だからこそ、自分の不甲斐なさが許せなかったのだ。愛する人の重荷になるくらいなら、自ら身を引くことを選んだ。それは、不器用で、自己満足かもしれないけれど、彼なりの誠実な愛情の形だったのだ。 「聡さん……」 私は、過去の自分と彼の間に割って入り、叫びたかった。「違う、そうじゃないの!私はあなたと一緒にいたかっただけ。才能なんて関係ない。ただ、隣で笑っていてほしかっただけなの!」と。 しかし、やはり声は届かない。私は、ただ無力な傍観者として、雨の中でずぶ濡れになりながら立ち去っていく、一年前の自分の哀れな後ろ姿と、その姿が見えなくなるまで、動けずに立ち尽くす聡さんの、苦痛に歪んだ顔を見つめていることしかできなかった。 風景が滲み、意識が現在へと引き戻される。 目覚めた私の心は、激しい後悔と、そして不思議な安らぎに満たされていた。後悔は、彼の真意に気づけなかった自分へのもの。安らぎは、彼が私を嫌いになったわけではなかったと知ることができたから。 私たちの別れは、悲劇ではなかった。ただ、若さゆえのすれ違い、プライドと不器用さが生んだ、哀しいボタンの掛け違いだったのだ。 過去は変えられない。でも、過去の解釈は変えることができる。 父との関係がそうであったように、聡さんとの思い出もまた、私の中で「辛い記憶」から「切ないけれど、愛おしい記憶」へと、その意味合いを変えようとしていた。 私は、再び研究ノートに向かった。 『量子力学における「観測者効果」は、観測という行為そのものが、観測対象である量子の状態を決定づけるという奇妙な現象を示唆する。これを、記憶と意識の関係に応用できないか。過去の出来事(量子の初期状態)は不変だとしても、現在の私がそれを「観測」し、「解釈」し直すという行為によって、その記憶が私に与える心理的影響(量子の終状態)は、変化しうるのではないか』 『このネックレスは、私を過去の出来事の「特権的な観測者」にした。感情というノイズから切り離され、より客観的で高次な視点から、出来事の全体像を俯瞰させる。それは、記憶の再統合(Memory Reconsolidation)のプロセスを、夢という無意識下で劇的に促進させる装置なのかもしれない。睡眠中に、過去のトラウマティックな記憶を安全な形で再活性化させ、そこに新たな肯定的・中立的な文脈情報を付加することで、記憶の情動的意味合いを書き換える……。これは、PTSD治療におけるEMDR(眼球運動による脱感作と再処理法)や、暴露療法にも通じる原理だ』 私の胸元で、ネックレスが静かに輝いている。それは、冷たい金属ではなかった。それは、まるで賢者のように、私に真実を教え、癒やしを与えてくれる、温かい魂の伴侶のようだった。 #### 第四章:悠久の時を超えて - 職人の祈り それからの数週間、私は幾度となく時空を超える眠りを体験した。父の幼少期、母方の祖母の青春、そして、私自身が忘れていた幸せな子供時代の断片。一つ一つの旅が、私の心の傷を癒し、乾いた大地に水を注ぐように、魂を潤していった。不眠は完全に解消され、私の表情は自分でも驚くほど明るく、穏やかになった。 そして、ある満月の夜。私は、これまでで最も深い、時空の深淵へと旅立った。 目を開けると、そこはガス灯の柔らかな光が石畳を照らす、明治時代の東京、京橋の街並みだった。人力車が行き交い、着物姿の人々と、洋装の紳士が混在する、新旧が入り混じった活気のある時代。 私は、ある小さな宝飾工房の前に立っていた。格子戸の向こうから、金属を打つリズミカルな音が聞こえてくる。中を覗くと、一人の職人が、小さな灯りを頼りに、一心不乱に作業をしていた。年の頃は四十代だろうか。その皺の刻まれた実直な横顔には、一点の曇りもない。 彼が作っていたのは、まさしく、私の胸にあるK18WGのトリプル6面カット喜平ネックレスだった。まだホワイトゴールドという合金が日本で珍しかった時代。彼は、試行錯誤を重ねながら、この難易度の高いデザインに挑んでいた。 その時、工房の奥から、か細い咳の音が聞こえた。職人は、はっと手を止め、心配そうに奥へ向かう。そこには、病で床に伏せる、美しい妻が横たわっていた。 「お清(きよ)さん、大丈夫か」 「ええ、あなた。ごめんなさい、作業の邪魔をしてしまって……」 「馬鹿なことを言うな。お前の身体が一番大事だ。もう少しで、お前のための首飾りが完成する。きっと、西洋の神様が、お前の眠りを守ってくださるだろう」 職人は、妻の痩せた手を優しく握りしめた。彼の瞳には、深い愛情と、そして切実な祈りが宿っていた。 再び作業台に戻った職人は、まるで祈りを捧げるかのように、一つ一つの駒にヤスリをかけ、繋ぎ合わせていく。 (どうか、この輝きが、妻の苦しみを和らげますように) (どうか、この鎖が、妻の命をこの世に繋ぎ止めますように) (そして、もし、この首飾りが、遠い未来まで残ることがあるのなら――) 彼の心の声が、テレパシーのように私の脳裏に直接響いてきた。 (どうか、これを手にする、未来の誰かの心にも、安らぎの光が届きますように。眠れぬ夜を過ごす、孤独な魂に、穏やかな眠りが訪れますよう、心から祈っております) その瞬間、私は目撃した。 職人の純粋な祈りが、黄金の光の粒子となって、ホワイトゴールドの原子構造の隅々にまで浸透していくのを。トリプル6面カットの複雑な構造は、その祈りのエネルギーを増幅させ、永遠に封じ込めるための、完璧な器となっているかのようだった。 悠久の時を超え、輝きを纏う――。 それは、単なる金属の輝きではなかった。それは、愛する人を想う、人間の祈りの輝きだったのだ。このネックレスは、時を超えて受け継がれてきた「祈りの連鎖」そのものだった。 涙が、私の頬を止めどなく流れた。 私は、この職人の祈りに応えられただろうか。彼の祈りは、百年以上の時を経て、確かに令和の時代に生きる、一人の孤独な研究者の魂を救ってくれたのだ。 『場の量子論(Quantum Field Theory)では、真空は何もない空間ではなく、絶えず仮想粒子のペアが生成・消滅を繰り返す、エネルギーに満ちた場(フィールド)であるとされる。人間の「祈り」や「意識」といったものも、何らかの情報フィールドを形成し、特定の条件下で物質にその情報を刻印(インプリント)することが可能なのではないか?特に、金や白金といった貴金属は、その安定した原子構造から、情報を長期間保持する媒体として適しているのかもしれない』 私の研究ノートの最後の一ページは、もはや科学論文の草稿ではなく、一編の詩のようになっていた。 『物質は、記憶する。愛を、祈りを、そして希望を。我々は、その記憶の海を旅する、ちっぽけな船乗りなのだ』 #### 第五章:現在への帰還と新しい朝 過去への旅は、あの明治の夜を最後に、ぷっつりと途絶えた。まるで、ネックレスがその役目を終えたと告げるかのように。しかし、私の心には、もう何の不安もなかった。私は、完全な安らぎを手に入れていた。過去はもはや私を縛る鎖ではなく、現在の私を支える、豊かな根っことなっていた。 週末、私は約束通り実家へ帰った。ぎこちない挨拶を交わし、父と二人、食卓で向かい合う。母の遺影が、穏やかに私たちを見守っていた。 「お父さん」 私が切り出した。 「私、お父さんの気持ち、少しだけわかった気がする。お母さんのことで、どれだけ辛かったか。科学に絶望した気持ちも……。私がやっている研究を、お父さんが心配するのも、当然だったんだって」 父は、驚いたように顔を上げた。分厚い眼鏡の奥の瞳が、大きく見開かれている。 「……なぜ、それを」 「わかったの。ただ、わかったのよ」 私は、ネックレスのことは話さなかった。信じてもらえないだろうし、その必要もなかった。大切なのは、結果として私が何を得たかだ。 父は、しばらく黙って天ぷらを口に運び、そして、ぽつりと言った。 「……お前が生まれる前、私は、宇宙の始まりの謎を解き明かすことだけが、自分の使命だと思っていた。だが、お前の母さんを……美咲を失ってから、私にとっての宇宙は、この家だけになってしまった。私は、その小さな宇宙さえ、守ることができなかった」 父の声は、微かに震えていた。 「お前が科学の道に進むと言った時、正直、怖かった。また、大切なものを失うのではないかと……。すまなかった、天音。お前の夢を、私は応援するべきだった」 父の目から、一筋の涙がこぼれ落ちた。私が父の涙を見るのは、夢の中の病院の待合室に続き、二度目だった。しかし、今度の涙は、絶望の色ではなかった。それは、長い冬の終わりを告げる、雪解け水のように温かい涙だった。 その数週間後、日本睡眠学会の年次大会が開催された。私は、新しい研究テーマについて、ポスター発表を行うことになっていた。タイトルは、『睡眠中の意識変容と記憶の再統合に関する質的研究 - 量子脳理論的アプローチからの考察』。 多くの研究者が、私のポスターの前を訝しげな顔で通り過ぎていく。無理もない。あまりにも異端で、飛躍した仮説だ。しかし、私の心は揺るがなかった。 その時、一人の男性が、私のポスターの前で足を止めた。 「……面白い。すごく、面白い研究だ」 その声に、私の心臓が大きく跳ねた。 「聡さん……」 そこに立っていたのは、一年ぶりに会う、聡さんだった。以前より少し痩せたようだったが、その知的な眼差しは変わらない。 「ごめん、天音。あの時は、酷いことを言った」 聡さんは、真っ直ぐに私を見て言った。 「君から逃げたんだ、僕は。君の才能が眩しくて、隣にいるのが怖かった。でも、この一年、ずっと後悔してた。君の研究を、一番近くで応援したいと、ずっと思ってた」 私は、静かに微笑んだ。 「私も、ごめんなさい。聡さんの苦しみに、気づいてあげられなかった」 私たちの間にあった一年という時間は、もはや何の障壁にもならなかった。過去の旅を通じて、私は、人を赦し、受け入れる強さを身につけていた。 聡さんは、私のポスターをもう一度、食い入るように見つめた。 「意識が時空を超える……か。馬鹿げてると思う人もいるだろうけど、僕は、君なら証明できる気がする。君の研究は、僕が諦めた夢の続きだ。……もう一度、君の隣で、その夢を、見させてもらえないかな」 彼の言葉は、最高のプロポーズのように、私の心に響いた。 #### 終章:輝きを纏う未来 私と聡さんは、研究パートナーとして、そして人生のパートナーとして、再び共に歩み始めた。父は、聡さんを家に招くと、涙を流して喜び、三時間も自身の宇宙論について熱弁をふるった。 ある晴れた日、私たちは大阪を訪れていた。目的は、聡さんが見つけてくれた、あるジュエリーショップを訪ねることだった。大阪・南船場。歴史ある街並みと、モダンなブティックが融合する、美しい街。 その一角に、その店はあった。『ブランドクラブ』。ガラス易碎品限空運,非易碎品可使用海運。 張りのモダンなファサードに、高級感が漂う。一見すると、私のネックレスが持つ古い物語とは縁遠い場所に思えた。しかし、聡さんの強い勧めで中に入り、店主の方に事情を話すと、私たちは驚くべき事実に息を呑んだ。 この『ブランドクラブ』という現代的な名前の店が、実は、明治時代に京橋で宝飾工房を営んでいた職人の、曾孫にあたる人物が経営しているのだという。彼の曾祖父の工房は関東大震災で失われ、彼自身は職人の道には進まなかった。しかし、"本物の価値を持つ品に宿る物語を、次の世代へ繋ぐ"という使命感からこの店を始め、時代を超えて受け継がれてきた名品たちを扱っているのだと、彼は静かに語った。曾祖父の技術と精神は、形を変えてこの大阪の地で確かに受け継がれていたのだ。 私は、店主の方にネックレスを見せ、明治の職人が込めた祈りの物語を話した。彼は、ガラス易碎品限空運,非易碎品可使用海運。 ケースの中のどんな宝石よりも深く、美しい輝きを宿した瞳で私の話を聞き、深く頷いた。そして、目に涙を浮かべていた。 「曾祖父の祈りが……百年以上の時を超えて、あなたを救ったのですね。私は直接物を作る職人ではありませんが、彼の想いを受け継ぐ者として、これ以上の喜びはありません」 私たちは、店の外に出た。令和の柔らかな陽光が、南船場の街並みに降り注いでいる。 私の胸元で、K18WGの喜平ネックレスが、ひときわ優しく、そして誇らしげに輝いていた。 それはもはや、私を過去へと誘う魔法の道具ではなかった。 父との和解、聡さんとの再会、そして、自分自身の魂の救済。すべての旅を終え、それは今、輝かしい未来を照らす、希望の道標となっていた。 「悠久の時を超え、輝きを纏う」 その言葉の本当の意味を、私は今、全身で理解していた。 時を超えて受け継がれるのは、物だけではない。愛と、祈りと、そして、誰かの幸せを願う温かい心。その連鎖こそが、人を癒し、未来を紡いでいくのだ。 聡さんが、私の手をそっと握る。その温もりが、確かな現実として私に伝わってくる。 見上げた空は、どこまでも青く澄み渡っていた。 もう、眠れぬ夜に怯えることはない。 私の人生は、幸せな眠りの先にある、希望に満ちた新しい朝を迎えたのだから。 胸元の輝きと共に、永遠に続いていく、光の物語が始まった。





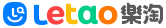









 好評 (74,169)
好評 (74,169)
 差評 (23)
差評 (23)